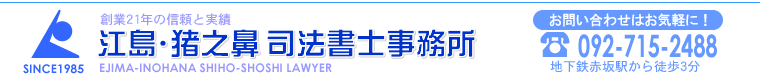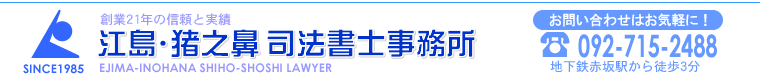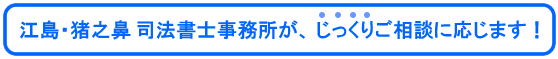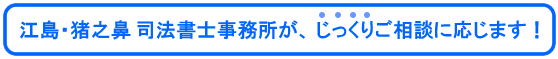TOPページ







|
 |
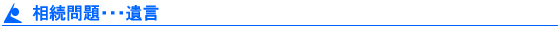
遺言は、自分の最後の意思を伝える手段のひとつです。財産にかかることだけでなく、残された人々に気持ちを伝えることもできます。
遺産相続の面においては、法律上は『遺言書』によって示された故人の意思を尊重しており、遺言者の意思が優先されます(法で認められた範囲内で)。
しかし、『法的に有効』とされる遺言書の書き方には『一定のルール』が定められており、これに反していた場合、残念ながらその遺言は法的効力を持ちません。
当事務所では、相続トラブルを未然に防ぐため、遺言に関するご相談も承りますので、お気軽にお尋ねください。 【遺言に関する情報は当ページ下部をご覧下さい】
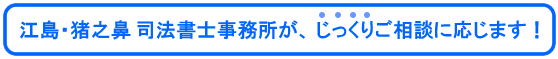

満15歳以上の者は遺言することができます。
遺言者はいつでも遺言を撤回することができます。
遺言の方法は方式が決まっており、普通方式と特別方式とがあり、ここでは普通方式について説明します。
| 自筆証書遺言 |
| 遺言者が全て自筆で記載すればよく、表現方法は問いません。タイプ・ワープロは不可。日付は年月日を記載しますが、書いた日にちが特定できればよく、「第何回目の誕生日」のような表現でも日にちが特定できるので有効です。但し、「○○年○月吉日」は認められません。この方法は簡単に作成ができるという長所がありますが、偽造・変造・毀損の危険も大きく、家庭裁判所における遺言書の検認が必要という手続の短所もあります。 |
| 公正証書遺言 |
| 公正証書によってする遺言です。証人二人の立会いが必要で、遺言者が遺言内容を公証人に口述し公証人が筆記する等の厳格な手続きが必要です。費用もかかりますが、遺言の存在・内容が明確で、偽造・変造・毀損の危険がなく、遺言の執行に家庭裁判所の検認を要しない等長所もあります。 |
| 公正証書遺言の必要書類 |
1: |
遺言者の戸籍謄本・印鑑証明書各1通 |
2: |
親・子・配偶者以外の人に遺贈・相続させる場合は、貰う人の住民票 |
3: |
不動産が対象物の場合は、登記簿謄本・固定資産税評価証明書 |
4: |
預貯金が対象物の場合は、通帳番号・証書番号をメモしていく |
5: |
その他、特に指定して相続させたいものがあれば、メモしていく |
6: |
遺言執行者を1名決めていく(親族でも構いません) |
7: |
親族以外の証人2名を連れて行く。 |
*手話通訳による遺言
|
手話通訳士等の通訳人と証人2名の立会いのもとで、遺言者が手話通訳を通じて遺言内容を公証人に伝えることにより、公証人が公正証書を作成します。 |
*筆談による遺言
|
証人2名の立会いのもとで公証人と筆談して公証人が公正証書を作成します。 |
*秘密証書遺言*
遺言者が署名・押印した証書(内容は自筆である必要はなく、ワープロ等でも構いません。)を封じ、証書に押した印鑑で封印します。遺言者が、公証人一人及び証人二人以上に封書を提出し、遺言書である旨、氏名・住所を申述します。公証人が、その証書を提出した日付、遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人とともに署名・押印するなど極めて厳格な手続きが必要です。これも家庭裁判所の検認が必要となります。 |
|
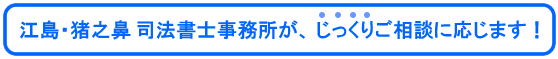
|
 |